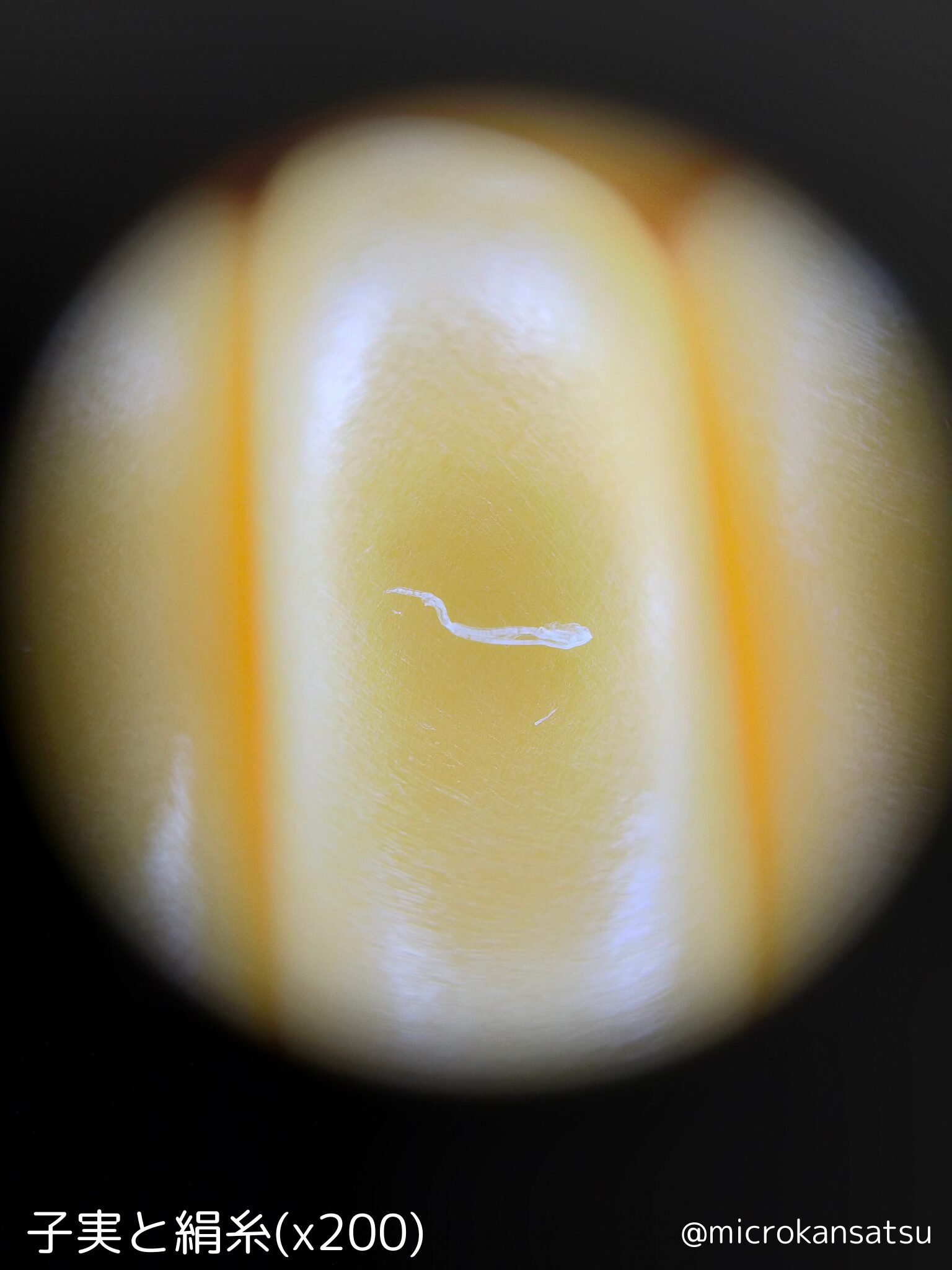こんにちは、ブログ管理人のミクロッティです
身近なものをスマホ顕微鏡で観察し、写真を集めてミクロ観察ずかんを作っています
今回は、夏野菜の「とうもろこし」を観察しました

とうもろこしの実の構造

とうもろこしの1つ1つの粒が「子実」で、全体は「苞葉(ほうよう)」に包まれています
1つの粒に1本のヒゲがついており、このヒゲは「絹糸(けんし)」と呼ばれるものです
絹糸に花粉がついて(受粉)、受精すると子実ができます
つまり、ひげの数だけとうもろこしの粒が存在するんですね!
1つの果実についている粒って、すごい数ですよね
地道に数えた人がいるのでしょう
苞葉(ほうよう)のミクロ観察
まずは、実を覆っている苞葉をミクロ観察しました
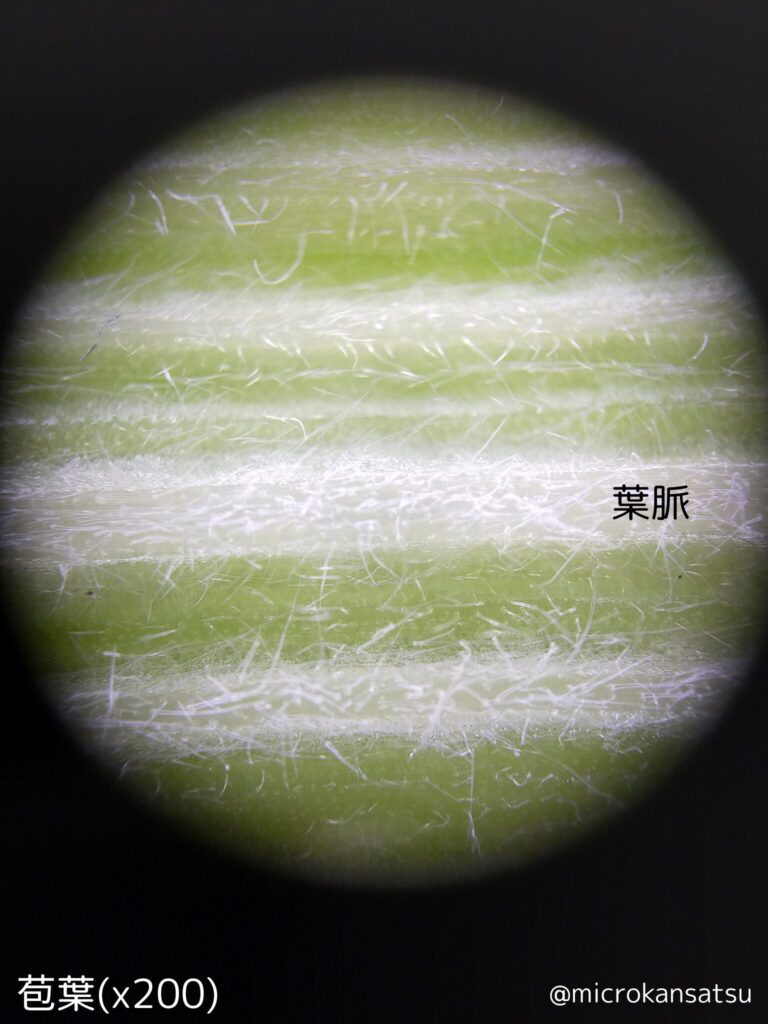

苞葉には太い脈が何本も平行に走っていました
とうもろこしはイネ科の植物なので、イネ科特有の平行脈の葉を見ることができました!
また、苞葉の表面には産毛がたくさん生えていました
これはおなじみのトライコームですね
ちなみに、とうもろこしには野菜以外にも様々な用途のものがあります
<トウモロコシの種類>
学名:Zea mays L.
和名:玉蜀黍
原産地:中央アメリカ
トウモロコシは、子実の性質や特徴によって次のように大別される
・スイート種(Z. mays var. saccharata)・・・野菜としてのトウモロコシ。糖質デンプンが多く、甘みが強い
・ポップ種(Z. mays var. everta)・・・ポップコーンの原料
・フラワー種(Z. mays var. amylacea)・・・ソフト種ともいう。粉にしやすい
・フリント種(Z. mays var. indurata)・・・加工してトルティーヤなどに使われる
・デント種(Z. mays var. indentata)・・・馬歯種ともいう。コーンスターチの原料
・ワキシー種(Z. mays var. ceratina)・・・粒の表面がツルツル。モチ性
(出典:農畜産業振興機構「トウモロコシの種類、製品の特性と用途」、トウモロコシノセカイ「とうもろこしの種類」)
絹糸(けんし)のミクロ観察
絹糸の先端は茶色くなっていました
花粉を受け取るという役目を終えて、枯れたのでしょう
一方、苞葉をむいて実の内側にあった絹糸は、白くてまだ元気そうでした

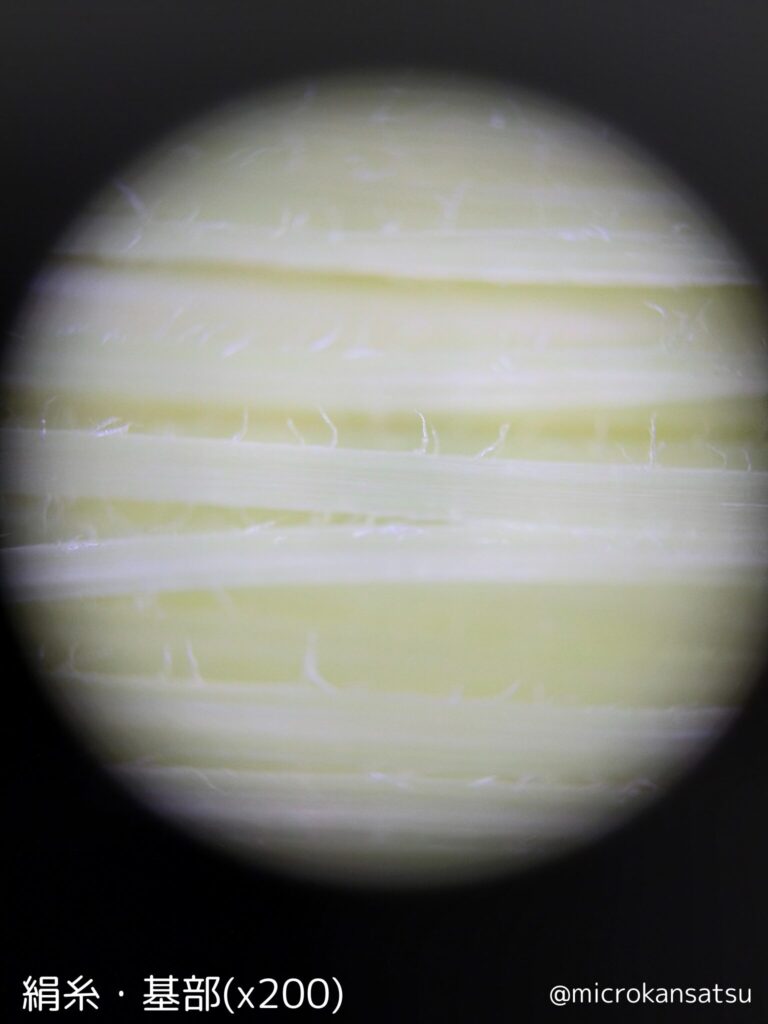
子実のミクロ観察
苞葉をむいていくと、子実と絹糸が見えました
絹糸のモジャモジャをよけると子実があらわになりました
途中で切れたのか、子実にくっついたままの絹糸も見えました!
本当に1つの子実に1本の絹糸がついているんですね
すごいなぁ。。。
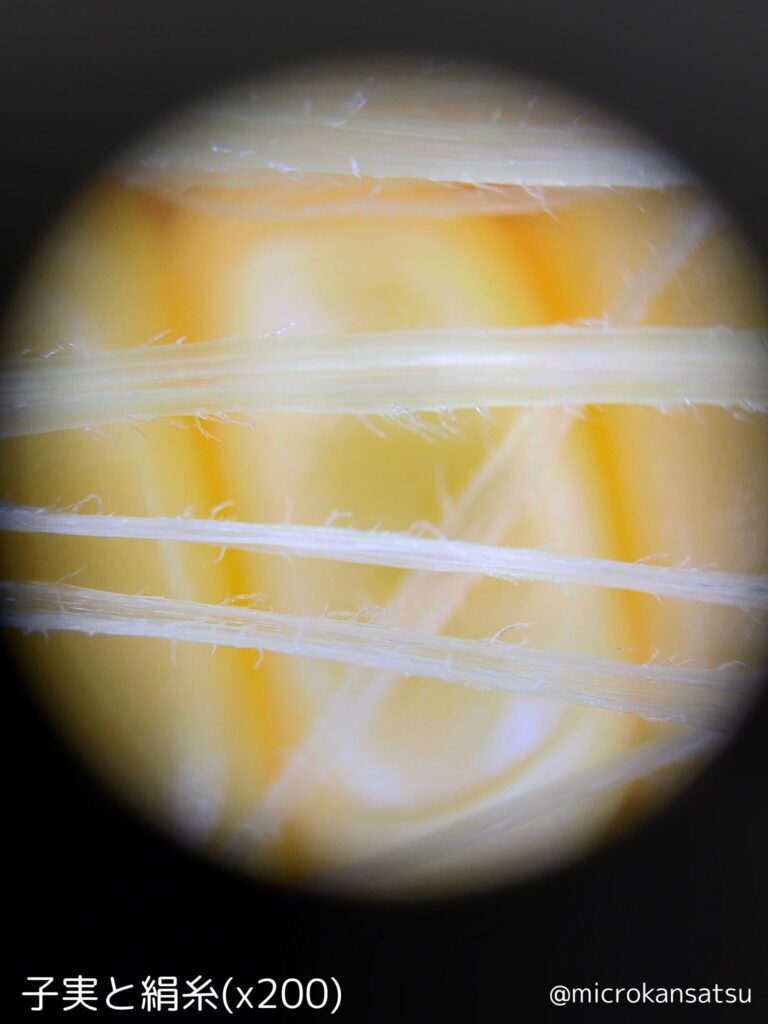

絹糸、刺さってる??
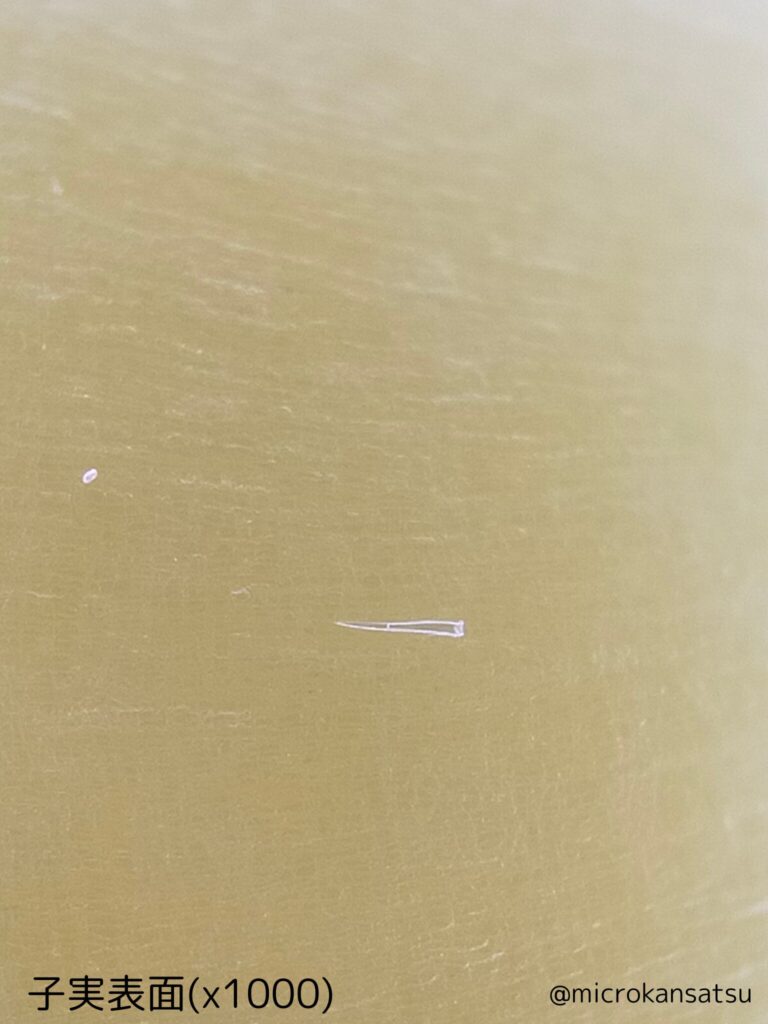
以上、観察おわり!
ひまわり、枝豆など、植物ずかんが少しずつ増えてきました
種や部位によって独特の形態をしているのは、とっても面白いです
これから季節に合わせて旬な植物を観察していきたいと思います!